9月議会一般質問参考資料
1 子育てナンバーワンの市を目指すための具体的施策の一つとして、第3子という条件を撤廃し、給食費の無料化をしてはどうか。
- 子どもの貧困という視点から。
・学校給食法=給食費は保護者の負担とすることを規定→市が補助することを禁止しているものではない。
| 現在の就学援助制度の対象者 |
| · 児童扶養手当を受けている人 ・市民税の非課税または市民税の減免された人
· 国民年金の掛金が減免された人 ・国民健康保険税の減免または徴収の猶予をされた人 · 個人の事業税の減免または固定資産税の減免された人 ・生活福祉資金による貸付けを受けた人 · 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者の人 · その他、特別な事情により経済的に困窮している人 ※上記の対象者については、給食費の実費を援助費として保護者に補助している。 |
厚生労働省の2012年調査
| 相対的貧困率=等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出)が全人口の中央値の半分未満の世帯員を相対的貧困者としている。相対的貧困率は、単純な購買力よりも国内の所得格差に注目する指標 |
子どもの6人に1人が貧困(相対的貧困率)一人親家庭の貧困率は54.6%。先進国で最悪の水準。
- 先進事例から、集中と選択(限られた予算の中で、あれもこれもではなく、あれかこれか)という意味で、無料化(全額補助)又は補助の拡大をしてはどうか。
岩倉市の類似団体(過去)である兵庫県相生市の事例:
平成23年4月1日「相生市子育て応援都市宣言」11の鍵
→新婚世帯家賃補助、定住者住宅取得奨励金、マタニティータクシークーポン、給食を無料化など
栃木県大田原市(平成24年10月から小学校の給食費月額4,200円、中学校の給食費月額4,900円を補助)
茨城県大子町=平成21年10月から小中学校無料化
他に、鳥取県伯耆町(ほうき)、山口県和木町、埼玉県小鹿野町、北海道三笠市
2 岩倉市の財産に対する諸々の見解を問う
| 2項道路(みなし道路)
建築基準法第42条第2項に規定されている道路で、建築基準法ができた昭和25年時点ですでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したものは、その道路の中心線から2mの線を道路の境界線とみなして、いずれ、その道路に接する各敷地がセットバックし、いずれかの日に4m幅の道路が実現することを政策目標とするもの。 |
| 道路の種類
公道、私道、里道(赤道・青道)、林道、農道、道路運送法上の道路、道路法上の道路(高速道路、一般国道、県道、市町村道)道路交通法上の道路、建築基準法上の道路(私道、公道の区別は問わない。) |
- 道路という財産について
総合計画の記述
狭あい道路や行き止まり道路を解消し、防災能力がある利用しやすい生活道路としていくため、計画的な道路整備を進めると ともに、セットバックや交差点の隅切りの確保などに努めます。
緑の基本計画における記述
市域に点在する各緑地を五条川などの河川や幹線道路の街路樹、緑道などで連絡し、ビオトープネットワークとなる緑の回廊を形成します。
- 新給食センターの賃貸借契約について
6月議会のやりとり
質新給食センターの民間委託に関連し、調理室や備品といった行政財産を含め、委託先とどのような契約をするのか。
答備品等の調達に向け、今後検討する。
9月議会財務委員会における答弁→①調理器具はすべて物品。物品の無償貸与の契約をする。②調理室(行政財産)の賃貸借は、調理業務の委託契約(請負契約)に包括(事実上の無償貸与)
その根拠→岩倉市財産管理規則第23条(分類及び整理)「物品は、次に掲げる区分により会計別に整理しなければならない」
しかし・・・・
指摘1)適正な請負と判断されるためには、請負業務の処理自体に必要とされる機械、資材等を発注者から借り入れる場合、請負契約とは別個の双務契約(賃貸借契約)が必要(独立性の原則による)である。「岩倉市財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例」第4条(物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償で貸し付けし、又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。)を適用しての無償貸与は、双務契約ではなく片務契約であり、独立性の原則に反する。
双務契約=当事者の双方が互いに対価的な債務を負担する契約。売買・賃貸借・雇用など。⇔片務契約(例:使用貸借、贈与)
指摘2)岩倉市財産管理規則の規定は、備品も含め、会計上きちんと整理することの趣旨であり、従属物的な備品は、地方自治法上の行政財産に当たる。
指摘3)調理室及び土地や部屋の固着物(従属物)(例:ボイラー室)は、行政財産である。本来、双務契約(賃貸借契約)を結ぶべきものを無償貸与とし、業務委託契約に含めることは、偽装請負である。
(3)太陽光発電のための屋根貸しについて
学校=行政財産かつ教育財産(管理は教育委員会)。屋上は、災害時の避難にも利用。
100円/㎡をベースに入札をかけ、各校バラバラとなっている。100円/㎡〜300円/㎡
この屋根貸し事業は、賃貸借契約を事業者と締結しているが、市当局の解釈としては、目的外使用料。しかし、100円を超えた部分は、雑入(条例の備考欄で、その他の料金を取ることができるという規定を適用→法規的に疑問)
また、実態は、賃貸借契約を締結している。申請に対する許可と双務契約をあいまいにしている。
❔この額や手法は適正かそして❔
| 屋根貸しでは、節電や災害時に役立つ。給食センターの民間委託では、子どもたちの給食について、民間のノウハウで安く、高品質な給食が提供できるという大義名分がある。しかしその裏側には、特定の事業者が長期間、市民の財産を利用し利潤を得るという事実も存在する。このことは極めて市政の運営の中では、重要な事項として、法律(地方自治法)では、市民の代表たる議会の十分な審議、議決を求めている。 |
これらのことがなぜ重要か
市当局の基本姿勢に、条例主義・議会の議決の重要性に対する考察が欠落→主権者である市民を蚊帳の外に置くこと
法律の規定
- 財産は、重要な市(市民)の財産
- 財産は、適正な対価なくして(無償を含む。)これを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない(行うときは、条例又は議会の議決が必要)。
- 特に、行政財産は、原則的に貸付け禁止(例外的に貸し付けることができる)」
平成18年の法改正で、その例外の範囲が拡大(市町村合併、行政改革、少子化など、時代の要請(自治体からの要請)に応じた改正)。
改正の趣意=地方自治体自らが使わない行政財産(スペース)について、民間事業者等に貸すことにより、有効に行政目的を達成し、他の市民の利用に差し支えない、反射的被害を与えないという条件のもと、貸付けができるとする考え方
(参考)地方財務実務提要((株)ぎょうせい)
| 平成17年最高裁判決(抜粋)
地方自治法237条2項は,条例又は議会の議決による場合でなければ,普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡し,又は貸し付けてはならない旨規定している。一方,同法96条1項6号は,条例で定める場合を除くほか,財産を適正な対価なくして譲渡し,又は貸し付けることを議会の議決事項として定めている。これらの規定は,適正な対価によらずに普通地方公共団体の財産の譲渡等を行うことを無制限に許すとすると,当該普通地方公共団体に多大の損失が生ずるおそれがあるのみならず,特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれもあるため,条例による場合のほかは,適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ,当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断にゆだねることとしたものである。このような同法237条2項等の規定の趣旨にかんがみれば,同項の議会の議決があったというためには,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するというべきである。議会において当該譲渡等の対価の妥当性について審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたというだけでは,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上議決がされたということはできない。 |
問「行政財産の安価な貸付けについて議会議決が必要か」
答「238条の4第2項の規定による貸付け等については,237条2項の規定を排除するものではない」として議会の議決が必要である。
※行政財産の目的外使用か、貸付けかの判断基準
- 短期(1年・2年)か長期か(事業者が安定的に事業を行う必要があるか)
- 賃貸借契約などを交わすか、申請に対する許可という一方的な行政処分か
※当該金額が変動する場合は、適正かどうかについて、議会の議決(議論)が必要
対価の妥当性については、個別の案件によらなくても、補正予算の議決でも良いが、形式的なものではだめで、妥当であることを認める議論が必要不可欠である(右の平成17年最高裁判決を参照)。
❔岩倉市では、なぜこうなるの
給食センターを民間資金で建てた場合→行政財産の貸付け(法律)
市が建てて委託した場合→施設の貸付けという概念を受け付けない。
3 政治教育の拡充を求める
選挙権の年齢引下げに伴い、地域の課題を考えることから始まり、政治的知識や判断力、主権者意識の醸成などの政治教育を両立させるための取組を小・中学校、高等学校で段階的に行うべきではないか。
事例
- 長野県選挙管理委員会→県教育委員会と協定を締結し、義務教育段階から主権者教育の充実を図る。
「選挙出前授業・模擬投票の実施・義務教育段階での選挙の意味や政治参加についての学習」
- 福井県選挙管理委員会→市町の選挙管理委員会と連携し、県内の公立・私立高校等に出向き、全校集会などの場を利用して18歳選挙権の意義などを説明。各校の要望により、出前授業や模擬投票を実施。
Etc.
選挙管理委員会とのコラボレーションも大事であるが、議会(議員)との協働も可能である(提言)。
関連記事
-

-
ほりいわお通信14を発刊しました!
9月議会が終わりました。平成28年度の決算認定が中心の議会です。問題のある案件と一般質問を中心に通信
-

-
岩倉市公の施設の使用料 値上げに関する考察
まず、平成30年度行政経営プラン推進委員会議事録を見ていただきたいと思います。 委員長:使
-

-
平成31年3月議会一般質問
岩倉市の将来都市像 「健康で明るい緑の文化都市」の緑の重要性を再度問う 北島の自然生
-
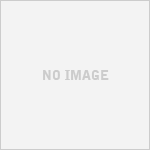
-
6月議会における一般質問内容予告
岩倉市議会会議規則で、次のように定められています。 第60条 議員は、市の一般事務について、議
-

-
政治倫理審査会の開催を求めました!
平成29年7月18日に、市民Jを名乗る匿名の方から議会事務局あてにFAXが届きました。 内容は
-
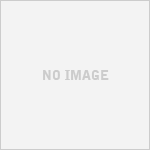
-
自殺対策計画推進委員会条例が提案されました(平成30年3月議会)
自殺対策事業では、平成28年度の9月議会(決算議会)で、私は、 「地域自殺対策事業なんですけれ
-
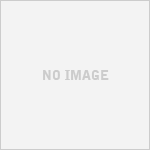
-
6月議会が始まりました。初日、懲罰動議を提出!!
3月議会から継続審査となっていた議案第26号(市役所駐車場にゲートを付けて、目的外使用料を徴収する内
-
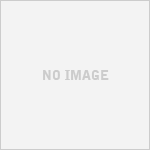
-
岩倉市副市長人事の案件は、やむなく退席(実質的には反対)
Facebookにも同じ記事を載せていますが、少し筆を加えたいと思います。 自治体では、教育委
- PREV
- 9月議会の一般質問
- NEXT
- ほりいわおニュース3を発刊しました!


