9月議会の一般質問
下記は、1時間という時間の中では、到底言い尽くせなかった部分も含まれています。回答についても、一部、省略しております。回答の詳細については、後日アップされる録画をご覧いただきたいと思います。
また、傍聴人の方に配布した参考資料を別にアップします。参考人の方からは、わかりやすいと評価いただきましたので、この記録が長くて、読みづらいという方は、参考資料の方を参考にしてください。
1 子育てナンバーワンの市を目指すための具体的施策の一つとして、第3子という条件を撤廃し、給食費の無料化をしてはどうか。
- 子どもの貧困という視点から。
(問)就学援助制度の対象者は、どれくらいいるのか。
(答)平成27年8月末 356人、9.9% 過去から増加傾向にある。
| 就学援助制度の対象者 |
| · 児童扶養手当を受けている人
· 市民税の非課税または市民税の減免された人 · 国民年金の掛金が減免された人 · 国民健康保険税の減免または徴収の猶予をされた人 · 個人の事業税の減免または固定資産税の減免された人 · 生活福祉資金による貸付けを受けた人 · 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者の人 · その他、特別な事情により経済的に困窮している人 |
(問)NHK報道番組ディレクターである新井直之氏の講演を聞いてきました。厚生労働省の2012年調査で子どもの6人に1人が貧困(相対的貧困率)であるという結果が出されたという事実が紹介されました。特に深刻なのは、ひとり親家庭。貧困率は54.6%。先進国で最悪の水準です。
| 相対的貧困率とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出)が全人口の中央値の半分未満の世帯員を相対的貧困者としている。相対的貧困率は、単純な購買力よりも国内の所得格差に注目する指標 |
離婚率が高まり、特にシングルマザーを中心に増え続けているとのことでした。
非正規雇用による低賃金、家庭内暴力、家庭内ネグレクトなど、家庭内部に潜む問題は様々で、助けを求めることができない状態に追いつめられていたりする中で、子どもたちの貧困は、大人によって隠されていると彼は言うのです。その結果、社会から孤立することが多く、不良行為に走ったり、孤独から逃れるために、同じような環境に置かれた同士が若くして結婚、妊娠したりという、いわゆる貧困の連鎖を生むと。
最近のむごたらしい、いじめによる自殺事件も例外ではないと分析し、いじめという社会問題の裏側に潜む、貧困という経済的な背景に目を向けるべきだと主張します。加害者が悪いとか、親が悪いとか、責任の所在を個人の問題として捉えるのではなく、貧困、格差社会という社会構造全体に目を向けるべきではないかということでした。
国は子どもの貧困対策法を施行し、2014年8月には、その具体的な施策をまとめた大綱を出した。しかし、社会全体が向っているのは、貧富の格差の拡大であり、この相対的貧困率は、数値としてそれを表しています。
1日の食事のうち、満足に食べられるのは給食だけという子どもたちが、見えないところに多く存在しているということを、実際の報道番組の映像を通して知りました。
岩倉市の就学援助の対象者の率と、子どもの相対的貧困率の乖離があるように思えます。岩倉市の相対的貧困率はどのようか。
(答)相対的貧困率は、把握していないが、母子家庭等は増えており、就労のことを考えると、厳しい状況であることは察することができる。
(問)兵庫県相生市は、平成22年度には、岩倉市の類似団体にもなっている、相生市では、平成23年4月1日に「相生市子育て応援都市宣言」を行い、子どもが健やかに育ち、楽しく、そして安心して子育てができるようにと、さまざまな子育て支援を展開しています。11の鍵ということで、新婚世帯家賃補助、定住者住宅取得奨励金、マタニティータクシークーポンなどとともに、市立幼稚園、小、中学校及び、特別支援学校に通う、市内在住の3~15歳の児童・生徒等を対象に豊富な献立メニューと栄養バランスのとれた給食を無料化しています。
岩倉市で無料化しようとすると就学援助や第3子分を差し引きして、現在よりざっと1億5千万〜6千万円の持ち出しになりますが、市長が掲げる「子育て世代ナンバーワン」という意味は、たぶん全国であり、相生市にできて、岩倉市ができないとは思えません。ナンバーワンというのであれば、給食の無料化について第3子という中途半端な補助ではなく、これくらいインパクトのある施策を打ち出してもいいのではないでしょうか。
全国には、相生市のほか、南アルプス市、茨城県大子町など、無料化している自治体も散見されます。
昨今の格差社会の拡大は、認めざるを得ない事実です。今回は、給食という題材を通して、貧困や格差社会を考えることでもありました。
給食費の無料化に対しては、食育という教育の一貫としてとらえ、経済格差という大人たちが作った社会構造の中で、少しでも罪のない子どもたちがそれを意識させることなく、伸び伸びと教育が受けられるようにすべきであると思います。先進事例から、集中と選択という意味で、無料化又は補助の拡大をしてはどうか。
(答)県内唯一第3子の給食の無償化について、年間約740万円の予算を掛け、行っている。また、経済的支援が必要な児童生徒に対しては、給食費を含んだ支援として就学援助制度を活用していただくよう働きかけている。この制度の運用では、前年度所得にとらわれることなく、離職等によって生活環境が急激に変化した場合などについても丁寧に相談を受け、対応している。完全無料化は、市全体の予算、施策を考える中、1億数千万円の額を市で負担することは、現実的には厳しいものと考える。
2 岩倉市の財産に対する諸々の見解を問う。
- 道路という財産について
(問)赤道や青道は、岩倉市にどのくらい存在するのか。また、台帳のようなもので管理しているのか。
(答)国有財産特別措置法の改正に基づき、国から贈与を受け市が管理している。台帳は、対象となった赤道等を特定するために作成した調査記録を国有財産一覧表として保管している。
(問)その台帳は、道路台帳のデジタル化した際に、デジタル化されているのか。
(答)デジタル化はしていない。
(問)赤道等の払下げをすることなしに、個人の財産として使用しているなどの実態はあるのか。全体の把握はしているのか。
(答)そうした実態は、非常に稀であり、市内全体の把握まではしていない。こうしたケースは、住宅の建て替えなどの際に表面化することで認知することになる。
(問)全体の把握はしていないとのことであるが、現在、懸案事項として折衝している案件はあるか。
(答)数件ある。
(問)今後の赤道等の整理計画はあるか。
(答)建て替えや開発の際に表面化し、その際に個別に対応している。処理には、1年から2年ほどかかり、計画的に整理していくことは、困難である。
(問)全体的な整理計画を持ち合わせていないし、今後も個別対応でいくという答弁であったが、市道も赤道も、市の財産であることは間違いない。しかし、現状では、ほとんどのものが払下げすることなしに個人の財産として利用されている状態を黙認、放置していることになる。払い下げを受ける人は、建て替えなどの私的理由からかも知れないが強制的に金銭を支払い、それ以外の人は、この先も永続的に使用することになる。中にはその赤道で営利を上げているという事例もあると聞いている。これは、公平性に欠けるのではないかと考えるがどうか。いっそ無償で譲渡するほうが公平・公正ではないか。過去払下げをしたものは還付しなければならないということで、できないのか。
(答)先ほどの答弁と同様。
- 狭隘道路に対する市の基本的な考え方を問う。
(問)総合計画の記述に基づく、基本方針等は定められているか。
(答)狭あい道路の拡幅については、住宅等の建設に伴い発生するセットバック部分を市に寄附していただけるようお願いしている。寄附に当たっては、寄附者にセットバック部分の分筆や舗装整備をしてもらうことを条件にしていることから、寄附者の負担が大きく、進んでいないのが現状である。基本方針等は定めていない。
(問)2項道路についても政策化すべきではないか。政策化とは、「4m幅の道路を実現することを政策目標とする」という法の趣旨を理解し、担当者が変わったり、その時々で判断基準がぶれたりすることをなくし、目標と計画を持つことに他ならない。進んでいない現状のまま、今後も進めていくのか。
(答)分筆や舗装整備などを市の方で行っていくことを検討していく。
(問い)2項道路は、建築基準法上の定義であるが、狭隘道路の政策化と大いに関係している。市民の財産である土地の建築要件、そして資産価値に関係するという面と、題目である狭隘道路をどうしていくのかという市の道路行政の両面がある。
2項道路か否かを最終的に決定するのは、特定行政庁たる愛知県であるが、データや実態を把握しているのは個々の地方自治体であり、実質的には市であることは、これまで担当にも確認したところである。
| 2項道路(みなし道路)とは
建築基準法第42条第2項に規定されている道路で、建築基準法ができた昭和25年時点ですでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したものは、その道路の中心線から2mの線を道路の境界線とみなして、いずれ、その道路に接する各敷地がセットバックし、いずれかの日に4m幅の道路が実現することを政策目標とするもの。 |
一方、2項道路か否かの判断は、その道路に接する地権者の声の大きさで判断されてはならないのはもちろんであるが、現実的に、行政庁の判断が同一の道について、2項道路としての取り扱いをしたりしなかったりし、全国では訴訟に発展している事例が散見される。総合計画に記述した狭隘道路の解消に向け、今後は、建築基準法の観点のほか、道路拡幅により通行人の安全性を確保する必要性というという観点も含め、総合計画に則り、方針を定めるべきではないかと考える。
- 道路行政はまちづくりと不可分であることについて
- 道路行政とビオトープネットワークの関係について問う。
ア 今後整備される道路について、ビオトープネットワークという視点で、しっかりと計画がなされているのか。
(問い)岩倉市は、平成8年4月に自然生態園をビオトープとして開設しました。ビオトープとは、bioという生物という意味と、topeという場所という言葉を合わせた造語であります。生物がその空間で生態系を維持しながら存続できる場所という意味です。
3月の代表質問の中でも、孤立化している自然生態園をビオトープネットワークでつなぐ方向性の答弁がなされています。その答弁は、総合計画そして、その下位計画である緑の基本計画が平成24年3月に作られていますが、そこにもきちんと示されております。
まず、その緑の基本計画における都市計画道路の街路樹に目を向けたいと思います。ビオトープネットワークを形成する要素として、五条川、学校ビオトープ、農地、そして街路樹などが挙げられます。この街路樹ということで言えば、自然生態園がオープンして間もなく、そのすぐ横の加茂伝法寺線の都市計画道路の工事が始まり、その当時、私は自然生態園の担当者として、生態園と農地がこの道路により寸断される状況について、自然環境のために、道路を地下に潜りこませたり、動物たちが行き来できるトンネルを作るという先進国であるドイツなどの事例などを参考に、当時は土木課だったと思いますが、なんとかならないかという話をしに行き、トンネルだけは作ってもらった経過があります。しかし、緑の基本計画では、きちんと、その都市計画道路の街路樹を整備することによって、緑の、そしてビオトープネットワークを形成することが記されています。今後整備される道路について、特に、緑化重点地区にもなっている萩原多気線は、五条川と自然生態園を結ぶ道路ですが、ビオトープネットワークという視点で、しっかり計画がなされているのか。
(回答)緑の基本計画では、緑の回廊を形成するため「岩倉駅から五条川周辺ゾーン」と「自然生態園周辺ゾーン」の2地区を緑化重点地区として設定している。桜通線や萩原多気線は、ビオトープネットワークの一翼を担っており、植樹帯等の設置を検討していきたい。
(問)植栽についても、ビオトープとしての機能を付加させるのであれば、専門家の意見が必要ではないか。
自然生態園を作ったときは、静岡大学の杉山教授に指導を受けて進めたわけですが、道路の計画について、ビオトープとしての概念を入れるとすれば、それなりの専門家の援助が必要かと思うがどうか。
(答)街路樹は市民の身近な緑であるが、生態系に配慮した位置づけが非常に難しく、有害な外来種生物の繁殖を促進する場合があり、苦情の増加につながることにもなる。よって、ネットワークの形成に当たっては、学識経験者など専門家の意見を求め、適切な調査・保全を行っていく必要があり、地域住民の理解も必要になる。先進地の取組状況も参考にしながら慎重に進めていく。
(問)道路行政の転換が必要ではないか(車中心から歩行者、自転車等も含めた道路行政へ)。
車中心の移動や通過を主目的とする道路、自転車や歩行者が低速で安全に移動できる道路、さらに、ビオトープや公園的な側面をもった人のコミュニケーションも可能となる道路や当該道路に近接する施設を含めた面的な計画をする必要があると思う。
街路樹は、市当局としては、維持管理など、手間やコストが掛かるということで敬遠しがちになると思います。具体的な計画遂行では、アダプトプログラム的な発想も必要かもしれません。また、先ほどの答弁にもあったように近隣住民を含めた意見集約や合意も必要になってきます。私が市役所に入ったまだ初期の頃、平坦でコンパクトなまちという岩倉市の特性を生かし自転車によるまちづくりが当時企画サイドで話し合われておりました。また、海外研修ということで、ドイツにも行く機会もいただき、自転車にも配慮した先進的な道路行政を学んでまいりました。しかし、その後、その研修を市政に反映することができず、自転車は駅前の歩道を埋める悪者に変わり、私自身も行政課で毎日自転車撤去の作業をしておりましうた。放置自転車対策も功を奏する一方、駐輪に対するモラルも向上し、駅前は、綺麗になりました。しかし、時は流れ、自転車道の整備はフィードバックできませんでした。日本も、今後、ただ単に、自動車がスムーズに通行できるだけのものではなく、自転車や歩行者、そして、全体的なまちづくりとして、都市計画道路や街路樹の整備を見ていく必要があると考えます。市当局の考え方をお聞きします。
(答)一足飛びにドイツ並みというわけにはいかないが、総合計画についても、その点に配慮し、見直していく方向である。
- 新給食センターの賃貸借契約について
(問い)先の6月議会で、新給食センターの民間委託に関連し、調理室や備品といった行政財産を含め、委託先とどのような契約をするのかという質問をしました。
おさらいの意味で、簡単に振り返りながら、再度、考え方を整理したいと思います。
地方自治法上、財産は、・財産・公有財産・物品・債権・基金に分類され、公有財産は行政財産と普通財産に分けられる。岩倉市には、物品の無償貸与ができるという条例の規定があり、給食センターのちょうど備品は、すべて物品で、無償貸与するということであった。物品単独であれば、それは成り立つけども、調理室や従属する備品は行政財産です。一方、偽装請負という問題もあるため、そうならないためには賃貸借契約を締結する必要が生じます。物品を無償で貸付することは、概念としては貸付ですが、無償の場合は、賃貸借契約、いわゆる双務契約にはならず、これは片務契約ということになります。
偽装請負にならないためという問題とは別に、地方自治の場合、議会の議決との関係が適切になされないといけないという点があります。結論から言いますと、短期間を想定し、申請に対する許可行為という行政処分として行う行政財産の目的外使用とは違い、賃貸借契約を締結する行政財産の貸付けは、長期間にわたるものです。公共の事務を遂行する大義名分があるけども、その裏側には、長期間事業者の経営を安定して行ってもらうという傍ら、特定の事業者が市民の財産を用い利潤を得るという側面も存在するわけですから、法律は、その契約金額が適切かどうか、条例に規定するか、あるいは、議会の議論と議決を求めているのです。このことは、平成17年の最高裁判例がわかりやすいので、読まさせていただきます。(参考資料参照)
他にも、議会の議決を経ないで行われた契約が無効となった判例もあります。
この2点の問題を解決する最も合理的な方法は、行政財産の貸付けに対する概念をゆるやかに解釈し、条例で貸付料を規定しておくことです。私個人としては、その都度、議会の議決や議論をする方が、議会や市民にとっては関心度が高まりますから、良いと思いますが。
基本的には、条例に額の定めがない場合、市の財産を利用させるのに、その対価を明示し、その対価が適正かどうかを議会や市民に明らかにする必要があるのである。確かに、物品については、単独で見れば無償貸与できます。しかし、調理室やボイラー室は行政財産であり、議会の議決なしに、長期間、私人に貸し付けるためには条例又は議会の議決が必要であると考えます。
(回答)無償貸与は片務契約であることは承知している。全体の契約については、今後検討する。
- 太陽光発電のための屋根貸しについて
(問い)太陽光パネル設置のための屋根貸しも、同様のことが言える。学校は、教育財産として教育委員会が管理するものであるが、以前、説明をしたのは環境保全課であった。なぜ、教育委員会ではないのか。
(回答)CO2削減や地球温暖化防止の観点から、公募から契約までを一元的に取りまとめるかを内部で調整を行い、その結果、環境保全課において公募をとりまとめることになった。学校施設においては、目的外使用との判断で教育長までの決裁で行っている。
(問い)行政処分という目的外使用許可としながら、賃貸借契約を結んでいる実態があります。目的外使用許可は、1年又は2年の短期であるが、それを更新することで、長期間の契約にとって変えてしまっています。
「目的外使用許可」は、行政上の許可処分であるので、公用・公共用の必要性が生じたときには、自治体が一方的に取り消しうるものである。この場合、特別の事情がない限り、使用者は補償を求めることはできません。(昭和49年の最高裁判例)
- 屋根貸しも長期間にわたる行政財産の貸付けであり、議決事項ではないのか。
「地方財務実務提要(ぎょうせい)」では,「行政財産の安価な貸付けについて議会議決が必要か」という問いに対し,「238条の4第2項の規定による貸付け等については,237条2項の規定を排除するものではない」として議会議決が必要であるとしています。
96条1項の各号の規定は、他に根拠条文があるものが多いですが、この条文は、予算の決定や決算の認定など議会の権限中最も基本的・本質的なものであることから総括的に列挙していると逐条解説にも書かれています。
シンプルに考えてみてください。法律では、普通財産・行政財産とも財産です。地方自治体自らが使わない財産について、市民や民間事業者等に貸すことにより、有効に行政目的を達成し、他の市民の利用に差し支えない、反射的被害を与えないという条件のもと、使用させ、貸付けができるとする考え方は、その財産の区分で大きく変わるものではありません。その趣旨で平成18年に拡大されたわけです。翌年のPFI法も行政財産の貸付けという概念で構成されています。PFIで建設した給食センターの事例は数多いわけですが、民間資金で建て市の財産にした場合は、貸付けで、市の歳入で建てた場合は、貸付ではないというのは、誰が考えても変です。
3 政治教育の拡充を求める
(問い)選挙権の年齢引下げに伴い、地域の課題を考えることから始まり、政治的知識や判断力、主権者意識の醸成などの政治教育を両立させるための取組を小・中学校、高等学校で段階的に行うべきではないか。
事例
- 長野県選挙管理委員会→県教育委員会と協定を締結し、義務教育段階から主権者教育の充実を図る。
「選挙出前授業・模擬投票の実施・義務教育段階での選挙の意味や政治参加についての学習」
- 福井県選挙管理委員会→市町の選挙管理委員会と連携し、県内の公立・私立高校等に出向き、全校集会などの場を利用して18歳選挙権の意義などを説明。各校の要望により、出前授業や模擬投票を実施。
先生が授業を行うと、政治的中立性の問題から、難しい。
選挙管理委員会とのコラボレーションも大事であるが、議会(議員)との協働も可能ではないか。
具体的な構想があればお聞きしたい。
(答)政治教育では、教師の思想・信条を出してはならないと思う。これまでの経験から、慎重になっている。むしろ、豊かな心を育て、正しい判断ができるような教育を進めることに、これまでどおり努力したい。
関連記事
-
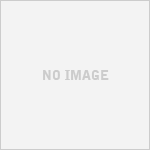
-
6月議会が始まりました。初日、懲罰動議を提出!!
3月議会から継続審査となっていた議案第26号(市役所駐車場にゲートを付けて、目的外使用料を徴収する内
-

-
ほりいわお通信15を発刊しました!
12月議会の報告や監査委員としての仕事を書きました。 フェイスブックで書いたように、元旦に、走
-

-
平成28年9月議会に一般質問を行いました。
9月20日に議会にて、一般質問を行いました。 1 公の施設における指定管理者制度に対する認識を問う
-

-
平成30年9月12日の厚生・文教常任委員会の報告①私学助成の請願
午前中は、高校の私学助成の請願・議案2本の審議でした。 請願の審議を中心に、報告します。
-
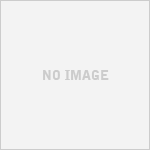
-
12月議会の報告(市長の政治資金規正法違反疑惑の総括)
%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%8
-
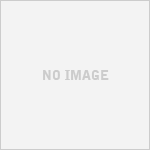
-
平成28年3月議会 代表質問(90分)を行いました
3月議会は、新年度予算のなど、52本もの議案が出されています。 その審議も大変なんですが、議会
-

-
5月臨時会が開催されましたー議会人事
5月9日から11日までの日程で臨時会が開催され、新体制が決まりました。 議長及び副議長は、選挙
-

-
12月議会の補正予算の質疑から
今回も、訴訟等委託料の増額補正予算が計上されています。70万円です。 議会が私に行った議員辞職勧告
-
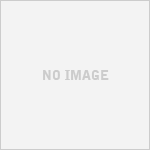
-
懲罰動議は、懲罰委員会へ!果たして結果は???
動議は成立し、直ちに懲罰委員会が設置されました。修正案は、再び、総務・産業建設常任委員会に付託される
- PREV
- 9月議会における本会議質疑の報告
- NEXT
- 9月議会一般質問参考資料


